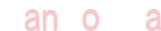医療の先進化や核家族化が進み、以前のように自宅で看取る機会は減り、病院で亡くなる方が年々増加しています。専門の終末期病棟が増えてきてはいますが、受け皿が足りず急性期病棟で看取りをしなければならない事例が多くあります。終末期ケアや家族ケアに慣れておらず、どのような看護をしたらよいか悩みを抱えた若いスタッフの参考になればと思い、事例に沿ってケアのポイントを紹介していきます。
終末期患者のニーズをどう受け止めるかが大切
医師から余命宣告を受けた患者さんの心情はどのようなものでしょうか。
- 悲しい
- 残された家族が心配
- もう気力がない
- 療を中断して楽になりたい
など様々だと思います。
しかし共通してやはり最後に何かやり遂げたかった事があると思います。
例えば、
- 1回でもいいから家に帰りたかった
- 最後まで治療を続けたかった
- 好きなものが食べたかった
など患者さんの思いに寄り添い、例えそれが実現困難な願いであっても少し工夫して気分転換の外出や試験外泊、アイスや奥さんの作った煮しめの差し入れ等、出来る最低限の事にトライしてみるだけでも、患者さんの表情や家族のやりきれない思いは少しでも軽減出来るのではないでしょうか。
中々、死を待つというシビアな期間に「最後出来るとしたらどんなことがしたいですか?」と尋ねるのはとても勇気が要る事ですが、患者さんのニーズを明確にし、そのニーズに基づいてケアすることが大切です。
例えば外出するならまずは疼痛コントロールや嘔気などの症状コントロールをどうするか、点滴や薬剤などをその間にどうするがなど、医師や看護師、薬剤師間でしっかりとアセスメントしカンファレンスを重ね、実現に向けて行動していくことがとても大切だと思います。
また、終末期患者だからといってこれが出来ない、あれが出来ないと医療者のパターナリズム化した認識が患者や家族のモチベーションを自然と下げている可能性があるので、まずは何か出来ることはないかという認識に変容させていくことも看護の一つではないかと思います。
事例:終末期だが最後まで治療を続けたい
ここで私が経験した事例をご紹介します。
膵臓癌末期の患者さんで手術後転移が見つかり、化学療法3rdラインまで進みましたが副作用で実施出来ず、その間に播種が進み余命は1か月でした。
その方の長女さんは某緩和ケア病棟で勤務されており、その方のために病床をキープしておくことが可能でいつでも転院可能という状況でした。
しかし、患者さんは決して首を縦に振らず、最後まで治療を続けたいと強い意志を表明されました。その治療というのが某ワクチン接種で病院から車で1時間ほどの診療所で週1回行われるものでした。
ワクチンは保険適応が効かないので、治療額は相当なものでしたがその治療に掛ける患者さんの思いは並々ならないものでした。その方は病気で奥様を早くに亡くされ、男手1つで3人の娘さんを育ててこられました。恐らく病気で弱気になる自分を見て欲しくない、最後まで戦う父の姿を娘さん達に見届けて欲しいという思いがあったのではないでしょうか。
しかしすでに転移は進み腹部や背部に強い疼痛を抱え、オピオイド持続投与に加え1時間ごとのレスキュー使用も行っていました。
起き上がりには介助を要し、下肢や体幹にも低栄養や肝転移のため浮腫を認め車椅子無しでの移動は困難でした。これだけの現状を踏まえると疼痛コントロールが不良で往復1時間をかけての外出はとても困難との見解が多数でしたが、本人やご家族の強い希望を受け、改めて疼痛状況をアセスメントし、オピオイド投与量を見直し外出時の疼痛コントロールを自己で痛むときにレスキューを使用しやすいPCAポンプに変更し、過剰使用とならないよう家族にも使用回数をメモして頂くよう協力を得ました。
また播種が進み経口摂取はほぼ不能で、低アルブミンが進み輸液量を絞った点滴の持続投与が必要でしたが、主治医を相談し点滴を夜間だけにして日中はなるべく繋がれるもののストレスがなく過ごせるよう工夫しました。
また家族にも嘔気出現時の対応などを説明し、主治医、緩和ケア医師、専門看護師、担当看護師、心理士、理学療法士、薬剤師が一同に集まり、少しずつ悪化していく病状に合わせてアセスメントを修正しながらカンファレンスを重ね、不安なく外出出来るよう準備をすすめました。
余命1ヶ月の宣告を受けてから1週間後に診療所への外出を行いました。
CTやレントゲン上では播種で消化管はほぼ通過困難となってましたが、治療の間だけは嘔気を訴えることもなく「行ってきます」と車椅子に腰を下ろし外出して行かれました。
最後の気力を振り絞るかのような、しかししっかりとした声でした。
外出出来たという喜びもあり不思議と痛みは感じなかったと外出先では1回もレスキューを使用する事無く過ごせたと患者さんの表情は穏やかでした。
体調を見ながら週1回の治療を3回行うことが出来ました。
しかしその間にも病状はすすみ腫瘍熱やオピオイド使用も相まって末期のせん妄症状を認めるようになり、通院を続けることが困難となり、間も無くして病院で息を引き取られました。
残された娘さん達は、「治療は出来て1回かなと思っていたけど、3回も通うことが出来て、本当に満足そうで良かったです。最後まで尽くしてくださってありがとうございました。」と声を掛けて下さいました。
当初余命1ヶ月ですでにDNRを取得していました。
しかし、どうしても諦めきれない患者さんの思いからこの外出計画を立案し、症状コントトールしながら実現する事が出来ました。DNR=いつ何が起こってもおかしくない状況と捉えがちで受け身になりがちですが、きちんとしたアセスメントに基づいて疼痛コントロールや嘔気コントロールを行えばまだまだやれる看護があると気付かせてくれた事例でした。また医療者側が受け身に回ることで逆にQOL向上の可能性を狭めてしまう危険性もあると感じました。
まとめ
終末期となると、どうしても医療者側としては負のパターナリズムを抱え患者さんに対し消極的になってしまいます。QOL向上のためにまずは率直に患者さんが今何を感じ、何がしたいかニーズを明らかにし、そのニーズを実現できる要素や困難とする要素をアセスメントし多職種と連携しながら実現に向け協力することが重要だと思います。
こんな記事/動画も見られています
こちらの本が読まれています

あなたに最適な施設
※記事に関連した施設です。
高木病院

神奈川県立循環器呼吸器病センター

行田総合病院
バックナンバー
- #2540精神科の患者さんのアセスメント
2024/04/23UP - #2539訪問看護師になるためには!?訪問看護師の理想と現実!
2024/04/22UP - #2538看護師が転職する企業の選び方のコツを種類から解説
2024/04/21UP - #2537役割に応じた看護師としてのアセスメント
2024/04/20UP - #2536失敗しない看護師転職のコツとは|転職の注意点や転職サイト選び方まで解説
2024/04/19UP - #2535夜勤のメリットデメリット、急変対応
2024/04/18UP - #2534家庭があるけど看護師を続けたい!両立のための職場の選び方を教えます!
2024/04/17UP - #2533看護師の転職を成功させるために重要となる職場の人間関係について
2024/04/16UP - #2532敗血症の兆候を採血データから見抜く!
2024/04/15UP - #2531精神科看護師が、魅力を解説!精神科の看護師になるには
2024/04/14UP - #2530看護師から一般企業への転職は可能?おすすめの転職先や面接対策まで解説
2024/04/13UP - #2529アセスメントを行う時のコツとは
2024/04/12UP - #2528ママさん看護師が仕事を続けるには?働き方や転職についても解説
2024/04/11UP - #2527看護師から一般企業に転職するには?経験を活かせる職種や転職成功のコツも解説
2024/04/10UP - #2526抗癌剤の副作用で吐き気が強い患者さんのアセスメント
2024/04/09UP - #2525社会人から看護師になる方法やその理由は?働きながら資格は取れる?
2024/04/08UP - #2524看護師が転職できるところはどのようなところがあるのか
2024/04/07UP - #2523ICT活用は看護アセスメントに重要!利用シーンを紹介!
2024/04/06UP - #2522社会人から看護師になるには?免許取得の方法から学校の選び方まで解説
2024/04/05UP
【看護師お役立ちコラム】への応募・問合わせ